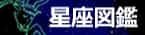シマヨシノボリ
| シマヨシノボリ ススズキ目・ハゼ科 |
.jpg)
.jpg) .jpg) .jpg)  |
| 標準和名 | シマヨシノボリ (縞葦登) | |||
| 分 類 | スズキ目・ハゼ亜目・ハゼ科・ゴビオネルス亜科・ヨシノボリ属 | |||
| 学 名 | Rhinogobius sp. | |||
| 分 布 | 日本や朝鮮半島、台湾など | |||
| 生息環境 | 河川の中流など | |||
| 全 長 | 5~8cm 程度 | |||
| シマヨシノボリは北海道を除く各地に分布しているハゼ科の淡水魚で、ほかのヨシノボリと同様、腹びれは吸盤状になっている。 国外では朝鮮半島や台湾などにも分布し、体側には5~6本のはっきりとした横縞があり、第二背びれやしりびれ、尾びれにも点列がある。 腹部は青っぽく、産卵期の雌では特に鮮やかになる。 また、ヨシノボリの仲間はいずれもよく似ているが、シマヨシノボリは、頬に暗赤色のミミズ状の縞模様があるのが特長とされている。 河川中流の平瀬に多く生息し、上流域や下流域にも見られるが、広い平野部の河川では見られない。 岩底や砂利底のような底質を好み、主に水生昆虫や底生生物を食べるが、雑食性で、付着藻類なども食べる。 産卵期は5~7月頃で、この時期の雌は腹部が濃青色になる。 産卵活動などはオオヨシノボリに似ていて、雄は雌を砂に埋まった石の下に巣に誘って、雌は天井に卵を産み付ける。 卵は孵化するまでは雄が世話をし、孵化した仔魚はすぐに海に下っていく。 仔魚は2~3ヵ月を海で過ごした後、再び河川を上っていくが、ため池やそれに繋がる河川では海に下らず、淡水で一生を過ごす陸封型のものもいる。 ヨシノボリの仲間は体色や体の模様に変化があるが、シマヨシノボリも体の模様などに変化があり、琉球列島に分布しているものは、九州より北のものと遺伝的に異なっていると考えられている。 近年は河川の改修や開発などによって、シマヨシノボリの生息数は減少している。 |
| ●ハゼ科の魚類へ ●このページの先頭へ |
.jpg) |
.jpg) |
.jpg) |