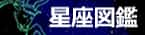チチブモドキ
| チチブモドキ ススズキ目・カワアナゴ科 |
.jpg)
.jpg) .jpg) |
| 標準和名 | チチブモドキ | |||
| 分 類 | スズキ目・ハゼ亜目・カワアナゴ科・カワアナゴ亜科・カワアナゴ属 | |||
| 学 名 | Eleotris acanthopoma | |||
| 英 名 | Spinecheek gudgeon | |||
| 分 布 | 日本や西太平洋沿岸域、インド洋の一部など | |||
| 生息環境 | 河川や汽水域など | |||
| 全 長 | 14~15cm 程度 | |||
| チチブモドキは、日本から東シナ海、南シナ海を経て、アラフラ海や珊瑚海、ミクロネシアなど、西太平洋の沿岸域のほか、インド洋ではアフリカ・マダガスカルにも分布していると言われている。 国内では千葉辺りから南で見られ、名前に「チチブ」と付いているが、チチブはハゼの仲間で、チチブモドキはカワアナゴ科に属している。 体は円筒形で、頭部はやや縦扁しているが、尾部へ向かって側扁している。 体色は灰色や茶色っぽいもののほか、黒っぽいものや淡いもの、緑色を帯びているものなど、変化が激しく、同じ固体でも環境や状況などによって変化する。 また、尾びれや胸びれの基底には暗色の斑があるが、普通は上下一対のようになっている。 一見して同属のものとはよく似ているが、カワアナゴとの違いは、眼から鰓蓋にかけて見られる放射状の暗色線がチチブモドキでは3本あること(カワアナゴでは2本)や、頭部下面に小さな白色斑が見られないこと(カワアナゴでは見られる)などの違いがあり、体つきもややずんぐりとした感じがする。 また、多種とは頭部にある感覚管の配置の違いによって判別できるとされている。 チチブモドキは河川の中流域から下流域、汽水域などに生息しているが、湿地や水田の用水路などでも見られる。 汽水域では水深5m辺りまでで見られ、河川などでは岩や流木、転石などの陰や植物の根際などに潜んでいることが多く、流れの緩やかなところで見られる。 主に夜間に活動し、水生昆虫や甲殻類、多毛類や小型の魚類、貝類など、様々なものを食べる。 産卵期は5~12月頃で、石の下などに卵を産み付ける。 国内では、近年の河川や汽水域、内湾などの整備・開発などにより、生息地が減少し、それに伴い生息数も減少している。 現在、チチブモドキは自治体によっては準絶滅危惧種(NT)などに指定されている。 |
| ●カワアナゴ科の魚類へ ●このページの先頭へ |