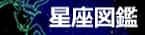ロウニンアジ
| ロウニンアジ ススズキ目・アジ科 |

 .jpg) .jpg) .jpg) |
| 標準和名 | ロウニンアジ (浪人鯵) | |||
| 分 類 | スズキ目・スズキ亜目・アジ科・アジ亜科・ギンガメアジ属 | |||
| 学 名 | Caranx ignobilis | |||
| 英 名 | Giant trevally | |||
| 分 布 | 太平洋やインド洋など | |||
| 生息環境 | 沿岸からやや沖合いの岩礁域など | |||
| 全 長 | 60~100cm 程度 | |||
| 別名・地方名 | メッキ、ヒラアジ、マルエバ、カマジャーなど | |||
| 備 考 | 第一背びれ・8棘、第二背びれ・1棘17~22条、しりびれ・2離棘1棘15~17軟条 | |||
| ロウニンアジは、西太平洋からハワイ諸島やライン諸島などの中部太平洋にかけて分布している大型のアジで、国内では本州中部・茨城辺りより南に分布している。 また、インド洋にも分布していて、紅海やペルシア湾、アラビア海を含むを含む、アフリカ東海岸からオーストラリア西海岸まで、幅広く分布している。 体は側扁していて、幼魚は円形のような体つきをしているが、成長に伴ってやや伸張し、成魚では卵円形をしている。 吻から頭部、第一背びれにかけては隆起していて、体高は高く、全体にアジよりもマダイのような体つきをしている。 尾柄は細く、しりびりの前方には2本の離棘があり、第二背びれとしりびれはほぼ相対していて、第二背びれとしりびれの軟条部は、鎌状に伸びている。 目の周りには脂瞼が発達し、胸びれ下部周辺には鱗がない。 側線は第3軟条辺りの下から直走していて、この部分にはよく発達した稜鱗(りょうりん/通称・ぜいご、ぜんご)が並んでいる。 若魚は、各地で「メッキ」と呼ばれるように、体色は銀白色で、腹びれやしりびれ、尾びれは黄色を帯びている。 成魚の体色は灰白色から灰黒色で、雄は全身が黒っぽいものが多い。 また、各鰭は黒みを帯びているが、しりびれは白く縁取られている。 一見するとギンガメアジに似た感じもするが、ロウニンアジには、ギンガメアジに見られる鰓蓋の黒班はなく、体高も高い。 また、ギンガメアジは「ナガエバ」と呼ばれることがあるが、これに対して、ロウニンアジは「マルエバ」と呼ばれることがあり、ヒラアジの中には、シマアジ、ギンガメアジ、オニヒラアジ、カスミアジ、ロウニンアジの5種があるが、ロウニンアジはもっとも大きく成長し、大きいものでは170cm、体重は80kg程のものが知られている。 成魚は、水深100m辺りまでの外洋に面した沿岸域で単独で生活しているが、水深180m辺りでも見られる。 岩礁域や珊瑚礁域の斜面などで見られることが多く、主に夜間になってからカニやエビなどの甲殻類や頭足類、魚類などを食べる。 また、幼魚や若魚は内湾や河口域などの砂底でもよく見られ、群れで生活している。 寿命は長く、飼育下では20年を超えることが知られている。 ロウニンアジは、若魚を中心に底曳網や定置網、地引き網などで獲られ、食用に利用されている。 白身の魚で、刺身や塩焼き、煮付けや唐揚げなどに利用され、おいしいものとされている。 しかし、漁獲量が少ないことから流通しているものは少なく、大型魚であることから、むしろ釣りの対象魚として人気がある。 この他、和名は大型で単独生活している様を「浪人」に例えて付けられたと言われているが、大型のものはシガテラ毒を持っているものが多いので、流通しないように指導されている他、南方の熱帯域のものは、若いものでもシガテラ毒を持っていることがあるので、食用に利用する場合は注意が必要である。 |
| ●アジ科の魚へ ●このページの先頭へ |