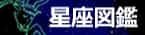ビワヨシノボリ
| ビワヨシノボリ ススズキ目・ハゼ科 |
.jpg)
.jpg) .jpg)  .jpg) |
| 標準和名 | ビワヨシノボリ (琵琶葦登) | |||
| 分 類 | スズキ目・ハゼ亜目・ハゼ科・ゴビオネルス亜科・ヨシノボリ属 | |||
| 学 名 | Rhinogobius sp. BW | |||
| 分 布 | 琵琶湖とその流入河川 | |||
| 生息環境 | 沖合いの深場など | |||
| 全 長 | 2~4cm 程度 | |||
| ビワヨシノボリは淡水性のハゼの仲間で、琵琶湖とその流入河川だけに自然分布している、琵琶湖の固有種とされている。 体は筒状で、頭部は側扁しているが、尾に向かっては側扁し、腹びれは吸盤状になっている。 体色は淡い褐色などで、暗色の斑が多数見られる。 鰓の下辺りは黄色く、成熟した雄の第二背びれとしりびれ、胸びれは大きく伸び、雌の胸びれ基底上部には青い斑点が見られる。 トウヨシノボリとはよく似ていて、以前は同種(トウヨシノボリ縞鰭型)とされていたが、ビワヨシノボリの第一背びれの先は尖らず、尾柄部には橙色の斑が見られないことなどから、現在は別種とされている。 また、腹びれの吸盤が縦に長く、鰭膜が薄いほか、第一背びれの前方には鱗がないなどの特徴がある。 尚、トウヨシノボリの縞鰭型と呼ばれるものでは、雄の第一背びれは伸びず、尾柄部にも橙色の斑が現れないなど、遺伝的にも異なっていて、現在はビワヨシノボリのほか、トウカイヨシノボリ、シマヒレヨシノボリとして別種とされている。 ところで、ヨシノボリの仲間は海や湖と川の間を回遊するものと、河川の中だけで生活する陸封型のものがいるが、ビワヨシノボリはどちらでもなく、産卵期以外は琵琶湖の沖合いを回遊しながら生活し、河川には遡上しないと言われている。 しかし、実際には流入河川の中流辺りまで遡上し、河川の中で一生を過ごすものもいると考えられている。 産卵期は6~7月で、沖合いから湖岸や流入河川の河口に集まり、いっせいに放卵する。 この時期の雄は暗色で、尻びれや鰓蓋の下方が黄橙色、顎の下が青くなる婚姻色を現し、石などの下に巣穴を掘って縄張りをつくる。 孵化した仔魚は湖岸近くで浮遊生活をおくり、成長と共に沖合いの深場に移動すると言われている。 沖合いでの生活の様子など、詳しいことは分かっていないが、食性はトウヨシノボリなどと同じで、付着藻類や底生動物、カゲロウやトビケラなどの水生昆虫の幼虫などを食べると思われる。 また、同じ時期に見られる個体の体の大きさにはほとんど差が見られないことから、ビワヨシノボリは一年で生涯を終えて世代交代を繰り返す年魚だと考えられている。 現在のところ、ビワヨシノボリの著しい生息数の減少などは見られないが、ブラックバスやブルーギルなどによる食害などが心配される。 尚、環境省のレッドリストでは「情報不足」とされている。 |
| ●ハゼ科の魚類へ ●このページの先頭へ |